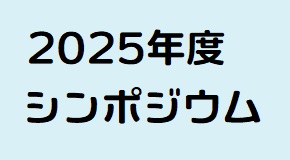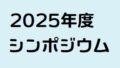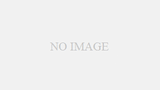日本酪農乳業史研究会2025年度
シンポジウム要旨
日 程:2025年6月7日(土)
午後1時40分~5時 シンポジウム、午後5時半~7時 交流会
場 所:日本獣医生命科学大学B412講義室
(〒180-0023 東京都武蔵野市境南町1丁目7−1)
JR武蔵境駅南口徒歩2分
テーマ:学校給食牛乳の歴史と意義
日本は世界的にも珍しい完全給食を実施し、その中で牛乳は重要な役割を果たしてきた。それは、児童生徒の健康・体力面と酪農の発展の両面における貢献である。本シンポジウムでは、こうした我が国の学校給食牛乳の歴史をたどり、その足跡と意義および課題について、多方面から確認、検討したい。
1.学校給食牛乳の歴史 中澤弥子氏(長野県立大教授 )
2.学校給食牛乳と食育 奥泉明子氏(一社 日本チーズ協会事務局長)
3. 学校給食用牛乳の政策の変遷 関 芳和氏(一社 Jミルク次長)
4.EUの学校給食牛乳の歴史と意義 平岡祥孝氏(稚内大谷高校校長)
学校給食牛乳の歴史 中澤弥子(長野県立大学教授)
日本の戦後の学校給食は、アメリカからの物資援助を受けて、東京都、神奈川県、千葉県の児童約二五万人に試験的に実施された1946年12月24日に始まった。翌年一月からは全国の都市部小学校を中心に約三六〇〇校、二九〇万人の児童に、深刻な食糧難の中、連合軍やララ物資の支給を受けて学校給食が行われた。そして1954年に「学校給食法」により、国の方針としてパンとミルクを中心とする給食が制定された。その後、1957年頃から牛乳が学校給食に利用されるようになり、国産牛乳の生産量の増大を背景に、1965年頃から脱脂粉乳にかわり牛乳に急激に変化した。現在、ほとんどの学校給食で牛乳が提供されている(2023年:学校数で小学校実施率99.1%、中学校91.5%)。これは、「学校給食法施行規則」第一条で、学校給食の区分として完全給食、補食給食、ミルク給食の三種類が定められ、すべての区分でミルクを給食すると規定されていることが根拠となっている。また、ミルクとは、カルシウムの摂取に効果的であるとの観点から、牛乳をはじめとする全乳及び部分的又は完全に脱脂した乳を想定しているとの文部科学省からの回答がある(内閣衆質二一三第六七号)。
一方、学校給食への米飯の正式導入が1976年に決定され,現在,米飯給食の実施率は完全給食を実施している学校数の100%に至り,週あたりの実施回数は平均3.6回〔2023年)となっている。
学校給食の無償化が2026年度から小学校で実施される予定であるが、文部科学省の実態調査では、学校給食の食材費は、都道府県別にみると2023年度の月額(実施回数が異なる)で、小学校が3,933円(滋賀県)~5,314円(福島県)、中学校が4,493円(滋賀県)~6,282円(富山県)と1.4倍の開きがある。
本報告では、学校給食牛乳の歴史の概要を述べ、新潟県三条市の取り組みの結果や最近の学校給食のアンケート調査結果を紹介し、学校給食牛乳の今後を考える情報提供を試みる。
学校給食牛乳と食育 奥泉 明子(一般社団法人 日本チーズ協会事務局長)
前職の一般社団法人日本乳業協会で25年半、「食育」という言葉が一般的ではなかった時から食育活動に携わってきました。特に2011年~2020年まで小中学校の食育出前授業を中心に教職員や学校栄養職員、PTAの講話も含む料理講習会や勉強会・研修会を実施していました。
学校給食における牛乳の重要性は、子供たちの成長に欠かせない栄養をバランスよく含んでおり、効率よく栄養を摂取できるということは周知の通りです。特にカルシウムは給食で50%が摂取できるように文部科学省により基準が示されており、牛乳は欠かすことのできない食材です。牛乳のカルシウムについては低学年でも既に知っていることが多かったです。
給食でどうして毎日、牛乳が出るのかをただ単に学んで知るのではなく、食育の授業を通して気づくことが大切だと考え、プログラムを作っていきました。乳牛や酪農の仕事を知ることで共感し、カルシウムだけではない、身体を作るたんぱく質や成長に不可欠なビタミン類も含まれること、混ぜ飲みなど低学年の子どもたちもできる実習を通して、牛乳って面白い、そして苦手でも味を変えたら飲めるなど新たな気づきを得ることで、特に冬場に多くなる飲み残しが減るなどの効果がありました。先生方には牛乳の食育は家庭科に関わる栄養面だけではなく、国語の学習単元に結びつけたり、牛乳パックのリサイクルで環境の学習ができるなど他教科との連携で多方面に広がる学習が可能なことや、野菜や果物と同様、農産物なのでいつも同じではなく成分が変わることで味も変化すること、乳牛が青草を食べる季節で風味に変化があることなども併せて伝えるようにしていました。乳業メーカーも工夫を凝らして食育出前授業などに取り組み、そして酪農家と一緒に「わくわくモーモースクール」を実施しています。
学校給食用牛乳の政策の変遷 関芳和(一般社団法人 Jミルク次長)
学校給食用牛乳は、飲用牛乳生産量の約10%を占め、酪農乳業においては安定的な飲用需要を確保するとともに、学校給食で毎日提供される牛乳は児童生徒が将来にわたり食生活の中で牛乳飲用の定着化を図るうえで非常に重要なチャネルと位置づけています。また、子どもたちの成長や健康を維持するためにバランスの取れた栄養摂取に大きな役割を担い、児童生徒の食生活を支える社会共通基盤となっています。
こうした学校給食用牛乳が定着した背景には、学校給食法をはじめ、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下、酪振法)など様々な政策によって推進されてきました。1954年に学校給食法が制定されますが、同じ年の酪振法の制定から、国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進を図るため、国内産の牛乳及び乳製品を学校給食への供給を促進するほか、集団飲用を奨励し、流通の合理化を促進するための援助など、酪農振興の一環としても学校給食用牛乳が位置付けられていきます。
酪振法に基づく学校給食用牛乳供給対策要綱(1964年文部科学省・農林水産省制定)では都道府県教育委員会による供給計画の作成、都道府県知事による供給価格及び事業者の決定を規定するなど、様々な法令や規程に基づいて学校給食用牛乳の安定供給が図られています。
農林水産省では、法令等に基づいて学校給食用牛乳供給事業で様々な支援策を実施しています。1957年に牛乳乳製品の需給調整対策の事業として、200cc当たり4円の単価補助から始まり、現在では、条件不利地域への輸送費補助を中心とした事業が実施されています。しかしながら1970年代には175億円であった事業費は現在では5億円程度と大幅に減少しています。
こうした政策や事業の変遷を振り返りつつ、話題となっている学校給食の無償化への対応なども含め今度の課題にどう向き合っていくか検討して参りたいと考えております。
EUの学校給食牛乳の歴史と意義 平岡祥孝(稚内大谷高等学校校長)
本報告では、欧州連合(European Union,EU)が、1977年に導入した学校給食用牛乳供給事業(School Milk Scheme,SMS)に関して、導入の背景と事業展開に焦点を当てて分析したい。
SMSが導入された理由は2点ある。1点目は市場政策目的である。短期的に牛乳・乳製品の消費拡大を通して余剰在庫を処分することであった。言い換えれば、域内生乳市場の需給均衡を図り、牛乳価格および乳製品価格を安定化させる政策意図があった。2点目は栄養政策目的である。教育機関において牛乳・乳製品の消費を促進させることを通して、園児あるいは学童に健康的な食習慣や、適切な栄養摂取習慣を定着させることであった。
しかし、過剰問題については、EUの酪農政策(Dairy Policy)として新たに、1984年から生乳クォータ制度(Milk Quota System)が導入された結果、生乳生産調整が進み、70年代後半から80年代前半にかけて増大した膨大な過剰は処理された。このように生乳生産をめぐる状況が変化したために、SMSは、その主たる事業目的を栄養摂取の改善に置くようになったのである。さらに、2011年に欧州会計検査院(European Court of Auditors)は、2009/10年度(school year)から実施されていた学校給食用果実・野菜供給事業(School Fruit Scheme,SFS)とSMSの事業統合に向けた検討を求めた。
児童・生徒の健康的な食習慣を促進するために、重点化した支援および教育面での充実・強化を目的としつつ、事業の効率化も視野に入れた事業統合案は、2016年2月にEU農相理事会(Council of Ministers)で承認された。そして2017年8月1日には生乳生産をめぐる状況が変化したために、学校給食用果実・野菜・牛乳供給事業(the EU School Fruit,Vegetables and Milk Scheme)として再構築されたのである。
学校給食用果実・野菜・牛乳供給事業では、健康的な食生活の推進、食農教育の普及、食品残渣削減への取り組みに重点が置かれている。また、当該事業は、農業部門が重要な位置を占めているEUの共通事業としての基盤を持ちつつも、加盟各国の特性を踏まえた食料政策や教育政策が反映されている。