2023年4月15日に開催されたシンポジウムの動画を配信いたします。こちらからご覧ください。
シンポジウム当日は、酪農学園大学を配信のメイン会場としながら、オンラインで約80名の方にご参加いただきました。ありがとうございました。
テーマ:北海道における酪農乳業の展開と協同組合の役割
現在の北海道酪農は、これまでの数年間と打って変わって、非常に厳しい経営環境に置かれている。その中で、減産に舵を切ったことで、ホクレンはじめ農協による共販体制が、畜産経営安定法による指定団体制度の見直しによる影響もあり、岐路に立たされている。この機会に、戦前、戦後を通して、協同組合による共販を作り上げてきた歴史を振り返り、その意義と役割について改めて考えたい。
方法:オンライン(終了後YouTubeで配信)
報告者(敬称略):
安宅一夫 (酪農学園大学)
井上将文(北海道大学)
高宮英敏(酪農乳業速報)
モデレーター 前田浩史(ミルク1万年の会)
ホスト 佐藤奨平(日本大学生物資源科学部食品ビジネス学科)
共同ホスト 小糸健太郎(酪農学園大学循環農学類国際経済学研究室)
酪農乳業史研究会 2023年度シンポジウム内容
1. 開会・趣旨説明
- イベント名: 酪農乳業史研究会 2023年度シンポジウム
- テーマ: 「戦前期北海道酪農乳業の展開と協同組合の役割」
- 登壇者:
- 第1報告:安宅一夫 氏(酪農学園大学 名誉教授)
- 第2報告:井上正文 氏(北海道大学 専門研究員)
- 第3報告:高宮義雄 氏(元・酪農乳業速報 社長)
- モデレーター:前田康弘 氏(ミルク1万年の会)
2. 第1報告:未曾有の酪農危機を歴史に学ぶ(安宅氏)
キーワード:4日会、デンマークモデル、協同組合
- 北海道酪農の黎明期:
- 幕末の開港(函館)により西洋文化が流入。1857年に栗本鋤雲(※文脈より修正:実際はライス領事)らが搾乳を試みる。
- クラーク博士(札幌農学校)が「デイリーファーミング(酪農)」の理念を提唱。肉牛ではなく乳牛(エアシャー種)の導入、サイロやビート栽培の重要性を説いた。
- 宇都宮仙太郎の功績:
- 「日本酪農の父」。アメリカで学び、最新技術(サイロ、アルファルファ栽培、ホルスタイン種導入)を持ち帰る。
- デンマークモデルの提唱: ウィスコンシン大学ヘンリー教授の言葉「デンマークを模範とすべし」に感銘を受ける。資源が乏しくても教育と協同組合で豊かなデンマークに倣うことを決意。
- 「4日会」と協同組合の発展:
- 1895年、宇都宮らが「札幌牛乳搾取業組合(4日会)」を設立。毎月4日に集まり勉強会を実施。
- その後、練乳会社への対抗や農民の自立のため、「札幌酪農組合」→「産業組合」→「北海道製酪販売組合(後の雪印乳業)」へと発展。
- 黒澤酉蔵と循環農法:
- 宇都宮の参謀として活躍。
- 循環農法(天地人): 牛・土・人の循環。ビートパルプを餌にし、糞尿を堆肥として土に還すことで地力を高める思想。
3. 第2報告:昭和戦前期における連作凶作と北海道酪農の形成(井上氏)
キーワード:産業組合、第2期拓殖計画、乳業資本
- 第1次大戦後の転換(宮尾農政):
- 豆類などの連作による地力減退(略奪農業)が深刻化。食糧基地としての役割を果たすため、地力回復策として「酪農+ビート」が推奨された。
- 宮尾道庁長官の下、宇都宮らの提言を受け入れデンマーク視察や畜産調査会への補助を開始。
- 乳業資本の進出:
- 森永、明治、大日本練乳などが進出。鉄道駅近くなどに工場を建設し、周辺農村からの集乳圏を形成(例:砂川、北見、名寄)。
- 政治的な繋がり(政友会など)も誘致に影響した。
- 第2期拓殖計画(1927年〜)と酪連:
- 憲政会政権下で「第2期北海道拓殖計画」が策定。黒澤酉蔵らが関わり、酪農振興が国策として盛り込まれた。
- 酪連(北海道製酪販売組合連合会)の台頭: 昭和恐慌時、民間資本が乳の受け入れを制限する中、酪連は国策的補助を受け、農民救済のために乳を買い支え加工(バター等)したことが評価された。
- 産業組合の役割:
- 各町村の産業組合が、酪農奨励や牛の導入、指導の主体となった。特に凶作地帯(同等の稲作失敗地域など)で、新たな営農手段として酪農が普及した。
4. 第3報告:北海道酪農発展の歴史と酪連の功績(高宮氏)
キーワード:アメリカの父・欧州の母、現場の苦闘
- 北海道酪農の系譜:
- 「技術はアメリカ(エドウィン・ダン、クラーク)から、精神・組織は欧州(デンマークの協同組合)から」学んだハイブリッド。
- 酪連設立の背景(関東大震災の影響):
- 大震災後、関税撤廃で安い輸入練乳が流入。国内乳業メーカーが買入れを停止し、生乳廃棄の危機に。
- 宇都宮・黒澤らが「農民が自らバターを作り販売する」ために製酪販売組合を立ち上げた(農民救済運動の側面)。
- 第2期拓殖計画と「牛100万頭計画」:
- 無謀な計画とも言われたが、個人の小農経営に牛を行き渡らせ、略奪農業から循環農法へ転換させる基礎となった。
- 地域ごとの成功事例:
- 根室: 元々は牛がいなかったが、昭和の凶作を機に相上道長官や黒澤らの指導で「根釧原野農業開発5カ年計画」を実施。日本一の酪農地帯へ変貌。
- 安平町遠浅: 開拓農民が「3年間は服を買わない」などの誓いを立て、借金返済と土作りに励み、日本初のチーズ工場などが作られた。
5. 総合討論(モデレーター:前田氏)
- 前田氏による整理:
- 1920年代:民間資本(明治・森永)による産業基盤形成。
- 1930年代:経済更生運動と第2期拓殖計画により、協同組合(酪連)主導の加工原料乳地帯としての性格が強まった。
- 主な議論・質疑:
- 北海道庁の役割: 官僚(石澤卓郎ら)もデンマーク派として動き、酪連設立時も強く支援した(「官」が協同組合を育てた側面)。
- 食糧増産 vs 農民救済: 当初は農民の生活を守るための「運動」的側面が強かったが、結果的に国の食糧増産政策(第2期拓殖計画)と合致し、予算がついたことで発展した。
- 土作り: 宇都宮・黒澤らに共通するのは、田中正造の影響を受けた「国土を穢さない、土を豊かにする(健土健民)」という思想。
- 現代への教訓(まとめ):
- 井上氏: 産業を守るためには、国策としての方向付けと適切な財政支援(補助金)の使い方が重要。
- 安宅氏: 危機においては、農民自身の自助努力と団結(協同組合精神)、そして社会奉仕の志が必要。
- 高宮氏: 「食糧は武器である」。基本である「土作り」と「循環農法」に立ち返り、国民に良質な食糧を提供し続けることが重要。
6. 閉会
- 閉会の挨拶。


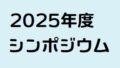
コメント